���q�������̐����ߒ��ɂ�������ِ���
���̓d�q�f�o�C�X�ւ̉��p
���k��w��w�@�E�H�w�����ȁE���p���w��U
�J�@�ތ�
���q�������̐����ߒ��ɂ�������ِ���
���̓d�q�f�o�C�X�ւ̉��p
���k��w��w�@�E�H�w�����ȁE���p���w��U
�J�@�ތ�
1. �͂��߂�
����܂ŁA���q�f�q�A���ȑg�D���A���邢�́A��ʓI�ɂ́A�{�g���A�b�v�A�v���[�`�Ƃ��Ēm���Ă��镪��́A���݂ł��i�m�e�N�m���W�[�̒��S�ۑ�̂P�Ƃ��č��̓��O�ő����̌����҂ɂ���Ċ�b�������s���Ă���B�{�g���A�b�v�A�v���[�`�̊��҂́A�r�[�j�b�q�ƃ��[���[���m�ɂ���Ĕ������ꂽ���q�E���q����\��L����STM�̏o���ɕ����Ƃ��낪�傫���B�܂�A�ő̕\�ʂ̌��q�\���A�X�ɂ́A�ő̕\�ʏ�ɋz���������q�E���q�̍\���A�Z�j�ɂ�錴�q�}�j�v���[�V�������̎������ʂ���A���Ȃ��Ƃ��A�ő̕\�ʂŌ��q�E���q���x���œ��قȍ\���̂����グ�鎖�������I�ɉ\�ƍl����ꂽ����ł���B
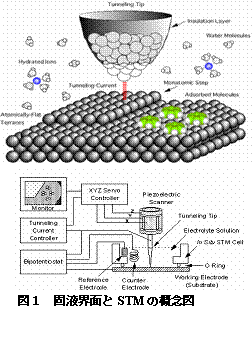 �{�u���҂́A����܂ŁA����ő̕\�ʂ̌��q�\���ڌ���\�ȑ����^�g���l���������Ɋւ��鑽���̌����������^�̊����ōs��ꂽ�̂ɑ��A���q�E���q���x���ł̏�w�NJF���ɋ߂��A�ő̕\�ʂ��t�̂Ɛڂ���u�ʼnt�E�ʁv�ɂ����āA�ő̕\�ʂ����q���x���Ŋώ@���邱�Ƃ��ł���t�̒��d�C���wSTM ���u�̌����������B�����āA���̑��u����g���A�d�������܂ސ��n�t���Ƃ��������ɂ����Ă��A���q���x���ŋK�肳�ꂽ����\�ʂ������̏d�v�ȋ����y�є����̂ɂ����āA�����^�Ɠ��l�ɁA���肵�đ��݂��邱�Ƃ��������B���̎��́A����܂ł̐���ő̕\�ʂɊւ��錤�����A�����^��Z�p�̎g�p��O��Ƃ��Ă��������l����ƁA�g�펯�h�����̂ł������B���̐V�������u�́A�u�ʼnt�E�ʁv���{���I�ɏd�v�Ȕ�����ł��鑽���̊w�p�E�H�ƕ���A�Ⴆ�A�d�C���w�A�R���d�r�A�G�}���w�A���q�z���A�\�ʏ����A���q�f�q�A�X�ɂ́A���̕������̌����ɕ��q���x���̏�����鋭�͂Ȏ�@����������łȂ��A�u�ʼnt�E�ʁv�̐V���Ȓn�������J�A�\�ʁE�E�ʉȊw�̔��W�̑傫�Ȍ����͂Ɛ����Ă���B
�{�u���҂́A����܂ŁA����ő̕\�ʂ̌��q�\���ڌ���\�ȑ����^�g���l���������Ɋւ��鑽���̌����������^�̊����ōs��ꂽ�̂ɑ��A���q�E���q���x���ł̏�w�NJF���ɋ߂��A�ő̕\�ʂ��t�̂Ɛڂ���u�ʼnt�E�ʁv�ɂ����āA�ő̕\�ʂ����q���x���Ŋώ@���邱�Ƃ��ł���t�̒��d�C���wSTM ���u�̌����������B�����āA���̑��u����g���A�d�������܂ސ��n�t���Ƃ��������ɂ����Ă��A���q���x���ŋK�肳�ꂽ����\�ʂ������̏d�v�ȋ����y�є����̂ɂ����āA�����^�Ɠ��l�ɁA���肵�đ��݂��邱�Ƃ��������B���̎��́A����܂ł̐���ő̕\�ʂɊւ��錤�����A�����^��Z�p�̎g�p��O��Ƃ��Ă��������l����ƁA�g�펯�h�����̂ł������B���̐V�������u�́A�u�ʼnt�E�ʁv���{���I�ɏd�v�Ȕ�����ł��鑽���̊w�p�E�H�ƕ���A�Ⴆ�A�d�C���w�A�R���d�r�A�G�}���w�A���q�z���A�\�ʏ����A���q�f�q�A�X�ɂ́A���̕������̌����ɕ��q���x���̏�����鋭�͂Ȏ�@����������łȂ��A�u�ʼnt�E�ʁv�̐V���Ȓn�������J�A�\�ʁE�E�ʉȊw�̔��W�̑傫�Ȍ����͂Ɛ����Ă���B
���������u�ʼnt�E�ʂł̃A�g���v���Z�X�v�Ɋւ����b�I�m������ɁA�ŋ߂ł́A���q��������p�����d�q�f�o�C�X�ւƌ�����W�J���Ă���B���̂P���L�@FET�̗L�@�����̍쐬�v���Z�X�ł���B����܂ŁA�L�@FET�́A�����œ����鑽�������������p�����Ă����B����ɑ��A�X�Ȃ�L�@FET�̓�������̂��߁A���ړ��x�����҂���錋�����̍����L�@�����u�ʼnt�E�ʁv�ō쐬����\�����������Ă���B�n�t�v���Z�X��ϋɓI�ɗp���Č��q�E���q���x���Ő��䂳�ꂽ����������@�ɒ��ڂ��Ă���A����܂ŁA�^������@����̂ɐi�߂��Ă������������@�Ƃ͑傫���قȂ�A����܂ŁA�قƂ�ǃf�o�C�X�ւ̉��p�ƌ����ϓ_�ł̌������Ȃ���Ă��Ȃ��A�����̉ۑ�ł���B
���݁A�Ȋw�Z�p�U���@�\�헪�I�n�����i���ƁiCREST�j�́u�V�����������ۂ⓮�쌴���Ɋ�i�m�f�o�C�X�E�V�X�e���̑n���v���������E����ᩓ̉��ŁA�����ۑ�u�ʼnt�E�ʂ̃A�g���v���Z�X�̉𖾂Ƃ��̉��p�v�̌�����\�҂Ƃ��āA�����Q�O�N�R���܂ł̂T�J�N�Ԃ̃v���W�F�N�g�����𐄐i���Ă���B
2.
����܂ł̌���
�ő̂Ɖt�̂��ڂ���u�ʼnt�E�ʁv�́A���w������������������b�Ȋw�I�ɂ����p�I�ɂ��ɂ߂ďd�v�Ȕ�����ł���B�@����܂ł́u�ʼnt�E�ʁv�̌������ʂ���ƁA���q�E���q�X�P�[���ł��@�E�ʍ\���A�A�E�ʔ����A�B���ȑg�D���A�ł���B�}�P�́A�ʼnt�E�ʂ̊T�v�}�Ɠd�ʐ���t��STM���u�̊T�O�}���������B
2.1�E�ʍ\���F
�@����F�ʼnt�E�ʂ��\������ő́i�����A�����A�����́j�\�ʂ̌��q�\���A�ő̕\�ʂɋz���������l�Ȍ`��E�@�\��L���镪�q�Q�̋z���P���q���̍\������v���̉𖾂ł���B�}�Q�͐��n�t���ɂ����Đ��E�ŏ��߂đ�����ꂽPt(111)����\�ʂ̌��q���ł���B
���̐��ʂ���APt�ȊO��Au, Rh, Pd, Ir���̋M�����P�����ɂ����Ă��A�t���[���A�j�[���@�Ƃ��Ēm���Ă���i��̓I�ɂ́A�Ή����ŐԔM���������̊e�w���ʂ�L����P�����d�ɂ��A�������ܐ��f�O�a�̒��������ŋ}�₷��j��@�ɂ���āA�d�������n�t���ōL���e���X�ƒP���q�X�e�b�v����Ȃ鐴��\�ʂ̘I�o�@�̊m�����s�����B����ɁA���ɂ̉𑜂����̐��ʂ́A�u�ʼnt�E�ʁv�̌����ɐV���Ȕ��W�̊�b�ƕ����������A�V���ȉȊw����Ƃ��āA�u�d�ɕ\�ʉȊw�v�̔��W�̂��߂̊�b���m�������B
�A�L�@���q�̋z���\��
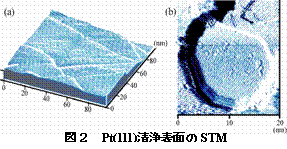
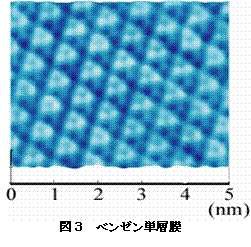 Rh(111)�ʂɋz�������x���[�����q�̗n�t���ł�STM�ώ@�ɐ��E�ŏ��߂Đ������Ă���i�}�R)�B�z�������x���[���́A��d�w�d�ʗ̈��c(2��3�~3)rect-2C6H6�\����(3�~3)-1C6H6�\���ւƓd�ʕω��ɂ�葊�]�ڂ��鎖�������������B��҂̍\���́AUHV���ł̃x���[����CO�̋��z���\���Ɠ���̂��̂ł��邪�A���n�t���ł͐����q��CO�Ɠ���������S���Ē����\�����`�����Ă�����̂Ɛ��肳�ꂽ�B���̌������ʂ[�Ƃ��A�d�Ɋ��ɋz�����������̗L�@���q�̍\�����𖾂����B����ɁC���E�f�P���q�w�ŏC�����������P�����\�ʂ�p����ƁC���G�ȕ��q�ɂ����Ă��L�@�P�����ɑ������鍂���z��̂Q�����L�@�������`���ł��鎖�����o���Ă���B�����̃|���t�B�����y�уt�^���V�A�j���U���̂̂Q�����P���q���̌`������\�I���ʂł���B�V�������������q�����̍쐻��@�ւ̓W�J�̊�b�����Ƃ��Ĉʒu�t������B
Rh(111)�ʂɋz�������x���[�����q�̗n�t���ł�STM�ώ@�ɐ��E�ŏ��߂Đ������Ă���i�}�R)�B�z�������x���[���́A��d�w�d�ʗ̈��c(2��3�~3)rect-2C6H6�\����(3�~3)-1C6H6�\���ւƓd�ʕω��ɂ�葊�]�ڂ��鎖�������������B��҂̍\���́AUHV���ł̃x���[����CO�̋��z���\���Ɠ���̂��̂ł��邪�A���n�t���ł͐����q��CO�Ɠ���������S���Ē����\�����`�����Ă�����̂Ɛ��肳�ꂽ�B���̌������ʂ[�Ƃ��A�d�Ɋ��ɋz�����������̗L�@���q�̍\�����𖾂����B����ɁC���E�f�P���q�w�ŏC�����������P�����\�ʂ�p����ƁC���G�ȕ��q�ɂ����Ă��L�@�P�����ɑ������鍂���z��̂Q�����L�@�������`���ł��鎖�����o���Ă���B�����̃|���t�B�����y�уt�^���V�A�j���U���̂̂Q�����P���q���̌`������\�I���ʂł���B�V�������������q�����̍쐻��@�ւ̓W�J�̊�b�����Ƃ��Ĉʒu�t������B
�Q�l�����FS.-L. Yau, Y.-G. Kim, and K. Itaya, "In
Situ Scanning Tunneling Microscopy of Benzene Adsorbed on Rh(111) and Pt(111)
in HF Solution", J. Am. Chem. Soc., 118, 7795-7803 (1996).
�B�����^���\�ʼnt�E�ʕ������u
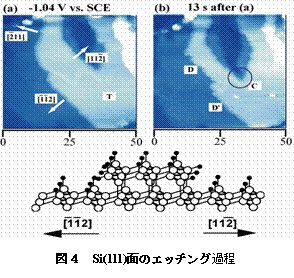 �@�����^��ƌʼnt�E�ʂɂ͑傫�ȑ���_��������̂��A���ʓ_������B�܂��A�����^�ł́ALEED�A�I�[�W�F���̊e��d�q�����@�����p���鎖���o����̂ŁA�\�ʍ\���𐳊m�ɋc�_����ꍇ�́A�����^�Ɏ��������āA�����̕\�ʕ��͖@�����p���铹������B�������A���̏ꍇ�́A�t�̒��ƒ����^�Ƃō\���ω��̋N����Ȃ��n�Ɍ�����B�܂��A�ʏ�́A���̈قȂ镵�͋C���ɑ��݂��鎎�����^�ɓ�������ۂ́A��C���������͕s�����K�X���͋C���o�R������Ղȕ��@������Ă��邪�A���̉ߒ��ŕ\�ʔ�ŁA�\�ʎ_�����i�s����̂ő����̒��ӂ��K�v�ł������B��\�҂炪�J�������������u�́A�t�̒�����قڊ����ɔ�ł��邱�ƂȂ������^�ɔ����ł��鑕�u�ł���B�܂��A�����^�Œ������ꂽ�\�ʂ��Ŗ����t�̒��ɔ����ł���B���̎�@��p����ƁA�ʼnt�E�ʂ̂��ڍׂȌ������\�ł���A�܂��A�^������@���̃h���C�v���Z�X�Ƃ̑���_�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��\�ł���B
�@�����^��ƌʼnt�E�ʂɂ͑傫�ȑ���_��������̂��A���ʓ_������B�܂��A�����^�ł́ALEED�A�I�[�W�F���̊e��d�q�����@�����p���鎖���o����̂ŁA�\�ʍ\���𐳊m�ɋc�_����ꍇ�́A�����^�Ɏ��������āA�����̕\�ʕ��͖@�����p���铹������B�������A���̏ꍇ�́A�t�̒��ƒ����^�Ƃō\���ω��̋N����Ȃ��n�Ɍ�����B�܂��A�ʏ�́A���̈قȂ镵�͋C���ɑ��݂��鎎�����^�ɓ�������ۂ́A��C���������͕s�����K�X���͋C���o�R������Ղȕ��@������Ă��邪�A���̉ߒ��ŕ\�ʔ�ŁA�\�ʎ_�����i�s����̂ő����̒��ӂ��K�v�ł������B��\�҂炪�J�������������u�́A�t�̒�����قڊ����ɔ�ł��邱�ƂȂ������^�ɔ����ł��鑕�u�ł���B�܂��A�����^�Œ������ꂽ�\�ʂ��Ŗ����t�̒��ɔ����ł���B���̎�@��p����ƁA�ʼnt�E�ʂ̂��ڍׂȌ������\�ł���A�܂��A�^������@���̃h���C�v���Z�X�Ƃ̑���_�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��\�ł���B
�Q�l�����FT. Yamada,
2.2�E�ʔ���
�@�����̓d�ɂ̃G�b�`���O�ߒ�
�@�����̃f�o�C�X�̍��W�ω�����������ɂ́A����������ȕ\�ʂ��`�����邱�Ƃ��d�v�ȉۑ�̈�ł���B�n�t���̃G�b�`���O�A�����鎼���G�b�`���O�́A���a�ȏ������Ńi�m�X�P�[���̕��������������\�ʂ��쐬�ł���Ɗ��҂ł���BSi(111)�ʂ̃G�b�`���O�ߒ��̓��ISTM������s���A�X�e�b�v�[�ŋN���锽���ٕ̈������𖾂����B�}�S�ɂ́A�P�R�b�Ԋu�ŕ߂炦��Si(111)�̉t���G�b�`���O�ߒ���STM���ł���B�X�e�b�v�͒P���q�X�e�b�v�ł���B�Q����STM���̔�r����A�_�C�n�C�h���C�h�I�[�̃X�e�b�v�ɑ��݂���Si���A���m�n�C�h���C�h�I�[��Si��葊�������G�b�`���O���i�s���邱�Ƃ��킩��B���̂悤�ɁA�ʼnt�E�ʔ����͋͂��Ȍ����G�l���M�[�̍��𗘗p���āA�I��I�̔����𐧌䂷�鎖���\�ł��鎖���A���炩�ɂ����B����A������W�ω�H���\�Ƃ��錴�q���x���ŕ��R�Ȕ����̕\�ʑn���ւƔ��W�����҂����B�{�����ł̕��q�������̐����E�n���̕��q���x���̉𖾂̌����͂̂P�ł���B�Q�l�����FK. Kaji, S.-L. Yau, and K. Itaya,
"Atomic Scale Etching Processes of n-Si(111) in NH4F Solutions:
In Situ Scanning Tunneling Microscopy", J. Appl. Phys., 78,
5727-5733 (1995).
2.3���ȑg�D��
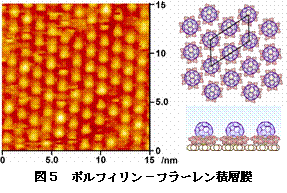 �ő̊�̍ŊO�w�̌��q�\���A����ɂ͊�\�ʏ�Ɍ`�������P���q�w�̗����͑������x�i�ƍl�����邪�A�X�ɂ��̐�́A���ȑg�D���A�{�g���A�b�v�̊ϓ_����A���Ӑ[�����q�ԑ��ݍ�p�𗘗p�����������s�����B�ϑw��w�ڂ̕��q�w�i�|���t�B�����j��ɓ�w�ڂ̃t���[�����P���q�����P�P�̊W��ۂ��ăG�s�^�L�V�����������邱�Ƃ��������B�}�T�ɂ́A����STM���ƍ\���̖͎��}���������B���̎����́A���̌�̑��w���̍쐻�A�X�ɂ́A�{�����J���ɐ�������邱�ƂɂȂ����B
�ő̊�̍ŊO�w�̌��q�\���A����ɂ͊�\�ʏ�Ɍ`�������P���q�w�̗����͑������x�i�ƍl�����邪�A�X�ɂ��̐�́A���ȑg�D���A�{�g���A�b�v�̊ϓ_����A���Ӑ[�����q�ԑ��ݍ�p�𗘗p�����������s�����B�ϑw��w�ڂ̕��q�w�i�|���t�B�����j��ɓ�w�ڂ̃t���[�����P���q�����P�P�̊W��ۂ��ăG�s�^�L�V�����������邱�Ƃ��������B�}�T�ɂ́A����STM���ƍ\���̖͎��}���������B���̎����́A���̌�̑��w���̍쐻�A�X�ɂ́A�{�����J���ɐ�������邱�ƂɂȂ����B
�ȏオ����܂ł̌������ʂ̊ȒP�ȊT�v�ł��邪�A�v����ɁA���������P���q�w�̖{���I�ȗ������猤�����s���ė����ɂ�������炸�A�P���q�w��ςݏグ�A�d�q�I�����]���̑Ώۂɂ��Ȃ���x�̖�����L����A���i�ʔ����̐����͐}�R�̌��ʂ��琄�����Ă��A�ȒP�ȋZ�p�ł͂Ȃ��B���̍����v��Ƈ@���w�ڂ̕��q�w�ɂ������̌��ׂ����݂���B�����ׂ̑�P�w�ڂ��쐬���鎖�́u�ʼnt�E�ʁv�ł�����߂č���ł���B�A�ݐςɂ͕��q�w�w�Ԃɒ������������ݍ�p���K�v�ł���A�����S�Ă̑w�ԂŒB������̂͗e�Ղł͂Ȃ��B������A�P���ȁu�{�g���A�b�v�v�̊T�O�ł́A���w�̕��q�w�̌`�����\�Ƃ��Ă��A�d�q�f�o�C�X�Ƃ��Ă̓����]���ɑς�������݂��������������쐻���鎖�͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B
�R�D���q�������̓��ِ��ƃf�o�C�X�ւ̉��p
�����P�S�N�P�O������J�n���ꂽ�ACREST�̌����ۑ�u�ʼnt�E�ʂ̃A�g���v���Z�X�̉𖾂Ƃ��̉��p�v�ł́A�����@���̐^��Z�p��p���������I���@�ł͂Ȃ��A�u�ʼnt�E�ʁv�����̓������ő�����p���A���i�ʂȁA�V�����T�O�Ɋ�����`�����@����X�������Ă����B�d�q�f�o�C�X�Ƃ��ẮAFET�ʂ̃^�[�Q�b�g�ɂ��Ă���B
FET�ő����̌������Ȃ���Ă���y���^�Z�����邢�̓��u�������̗L�@�������u�ʼnt�E�ʁv�����p���č쐻����ƁASi�AGaAs���̖��@�����̌����ɔ�ׂĂ��A�g�ُ�h�Ƃ��v����ǎ��Ȍ������������������炩�ɂȂ����B���݁A����ꂽ�����̕��q����Ȃ�A������u���q�������v��X-���\����́A��ڐG���q�Ԍ�����(NC-AFM�j�A�e�핪���@�ɂ���āA�ʼnt�E�ʂł̌����̐����ߒ��̓��������炩�ɐ������i�K�ɓ��B���Ă���B�܂�A�����@�ł͒B���ł��Ȃ��u�ʼnt�E�ʔ����̐V���ȓ����v�̔����ƌ����ĉߌ��ł͂Ȃ��B�u�ʼnt�E�ʁv�ō��ꂽ���q�������̃o���N����ѕ\�ʂ̊��S���̎��́A�ʂ̊ϓ_���猾���ƁA�u���ȑg�D���̋��ɂ̎p�v�̂P�ł��邱�Ƃ������������Ă���B
FET�̓����́A�������̓d�q���邢�͐��E�̈ړ��x�ɂ���Č��肳��Ă���ׁA�����ׂɋ߂����S�����鎖�́A�ړ��x�ƌ����̖{���I�����Ƃ̑��ւ�m���ł��ɂ߂ďd�v�ȈӋ`�����B�܂��A�{�ۑ�őΏۂƂ���d�q�f�o�C�X�́AFET�Ɍ��炸�A���ʂȖ��������A�L�@EL�A�L�@���z�d�r�A�X�ɂ͈�ʓI�ɁA�L�@�����́A���̂ƂȂ镪�q�������̕����𖾂ɂ��v��������̂ƍl������B�܂��A�ʼnt�E�ʂ�p����ƁA�������鎖�̂ł��Ȃ��A�Ⴆ�A���̕������̌��������\�ł���A���̉��p�͈͂͂��Ȃ�L�������Q�ɋy�Ԃ��̂ƍl������B
�ȏ�̗l�ɁA��X�́A����܂Ŕ|��ꂽ�u�ʼnt�E�ʁv�̓������ő�����p���A���q�E���q���x���ł̕��q�z���������{�T�O�Ƃ��āA����܂łɂȂ����i�ʂ̕��q�������A���邢�́A���q���P�����̉t�������@�̊m����ڎw���B�܂��B���������ߒ��̉𖾂��d�v�ȉۑ�ł���B����ɁA���ł̒��ڌ��������ߒ��q���x���Ō�������B���ꂪ���炩�ɂ����A�d�q�f�o�C�X���ɒ��ڕ��q�������𐬒������鎖���\�ƂȂ�B�����̗L�@�f�o�C�X�̓��������コ���邽�߂ɂ́A�L�@�������{���������ړ��x��������K�v���L��A���q��������p�����A������L�@FET�A�L�@EL�A�L�@���z�d�r�A�X�ɂ͈�ʓI�ɁA�L�@�����́A���́A���̍����I�ȕ]�����\�ł���A���f�o�C�X�̊J���ɏd�v�Ȏw�j��^������̂ƍl������B
3.1�@���q���P�����̉t�������@
�@���F�����Y�����f
�y���^�Z���F�@�L�@�E���@���q����Ȃ镪�q���������邢�͒P�����̐����@�ɂ́A��ʓI�ɁA�C������̏��ؖ@�Ɖt�������@���m���Ă��邪�AFET�AEL�A���z�d�r���̓d�q�f�o�C�X�̂���܂ł̖w�ǂ̌����E�J���ł́A�����@�ɑ�\�����C���@�ŗL�@����������Ă���B�������A����܂ł̗L�@�f�o�C�X�J���̌o�܂���A�t�����������@�́A���܂�ϋɓI�ɂ͌�������Ă��Ȃ��B�L�@FET�A�L�@EL�̍ŋ߂̌����E�J���ł́A�ꕔ�ɉt���@�̒�Ă��Ȃ���Ă��邪�A���Y�����҂����o�����A�t���@�̓����܂��Ă̒�Ăł͂Ȃ��B
�{�����ɂ����āA�t���@�œ�����l�X�Ȍ����̍\�����A��ɕ\�ʁE�E�ʂ̏d�v������A�ʏ��X-���\����͂̑��ɁA��ڐG���q�Ԍ������iNC-AFM�j��p���鎖�ɂ��A�t���@���瓾��ꂽ�����̋ɂ߂ďd�v�ȓ������B
�}�U�ɂ́A�L�@FET�ōł��������i��ł���y���^�Z���̏������̓T�^�I��AFM���ł���B�ώ@�̈��500 nm�~500 nm�ł���A�����̈�S�ʂɓn���ē���̃����t�H���W�[�ł������B�}�V�͐}�U��AFM�����Ɉ����ꂽ����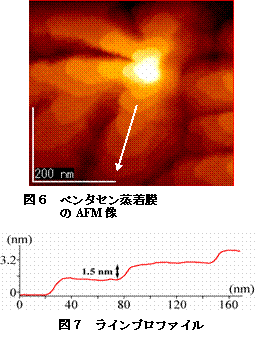 �ɉ����Ă̕\�ʂ̉��ʂ��������C���v���t�@�C���ł���B��{�I�ɂ́A���������Ă�����̂̃X�e�b�v������1.4~1.6 nm�ł���A�X�e�b�v�Ԃ̃e���X�́A���q���x���ŕ��R�ł���B�e���X���́A�e�w�ɂ���ĈقȂ邪�A10~30 nm���x�ł���B�����@�ɂ���Ă������������q�I�ɕ����ȃe���X�ƒP���q�X�e�b�v����Ȃ�\�ʍ\���ł��邱�Ƃ́A���q�Ԃ̑��ݍ�p���傫���A�w��ɐ�������X���̍������q�������ł��鎖���������ꂽ�B
�ɉ����Ă̕\�ʂ̉��ʂ��������C���v���t�@�C���ł���B��{�I�ɂ́A���������Ă�����̂̃X�e�b�v������1.4~1.6 nm�ł���A�X�e�b�v�Ԃ̃e���X�́A���q���x���ŕ��R�ł���B�e���X���́A�e�w�ɂ���ĈقȂ邪�A10~30 nm���x�ł���B�����@�ɂ���Ă������������q�I�ɕ����ȃe���X�ƒP���q�X�e�b�v����Ȃ�\�ʍ\���ł��邱�Ƃ́A���q�Ԃ̑��ݍ�p���傫���A�w��ɐ�������X���̍������q�������ł��鎖���������ꂽ�B
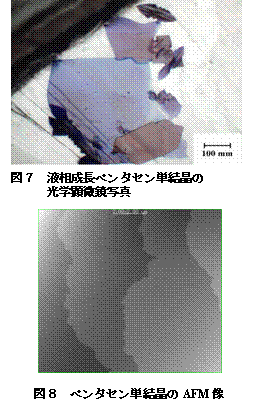 �}�X�́A���ʂ��猩��������X-����͂��瓾��ꂽ�\���ŗL��A�y���^�Z���̒��������X�����ϑw�\���ł���B�\�����疾�炩�Ȃ悤�ɁAAFM�Ŋώ@���ꂽ�X�e�b�v�́A�X�Δz�������y���^�Z���̑w�Ԃ̍����ɑΉ����Ă���B
�}�X�́A���ʂ��猩��������X-����͂��瓾��ꂽ�\���ŗL��A�y���^�Z���̒��������X�����ϑw�\���ł���B�\�����疾�炩�Ȃ悤�ɁAAFM�Ŋώ@���ꂽ�X�e�b�v�́A�X�Δz�������y���^�Z���̑w�Ԃ̍����ɑΉ����Ă���B
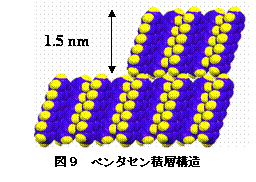 ����A�}�V�́A�W�N���[���x���[���n�t������ꂽ�y���^�Z���������}�C�J��ɌŒ肵�����̌��w�������ʐ^�ł���B�����̑傫���͖�0.5 mm�̊p�^�����Ă���B���̒������̌����̖����́A300 nm�Ɣ��ɔ����B�܂�A�����̃}�N���̌`�炷��ƌ����́A�����̉�������ɑ������x�Ő������A���ݕ����̐������x�͔��ɒx���ƌ��_�����B�����͌��w���������ł͋ψ�ł���B
����A�}�V�́A�W�N���[���x���[���n�t������ꂽ�y���^�Z���������}�C�J��ɌŒ肵�����̌��w�������ʐ^�ł���B�����̑傫���͖�0.5 mm�̊p�^�����Ă���B���̒������̌����̖����́A300 nm�Ɣ��ɔ����B�܂�A�����̃}�N���̌`�炷��ƌ����́A�����̉�������ɑ������x�Ő������A���ݕ����̐������x�͔��ɒx���ƌ��_�����B�����͌��w���������ł͋ψ�ł���B
�}�W�́A���̌�����NC-AFM���ł���B�����͈͂́A�}�U�Ɏ�������������AFM���̊ώ@��葊���L���B�����̃X�e�b�v�́A��ɏq�ׂ��X�����y���^�Z���̒P���q�����ɑ�������B
�@���M���ׂ��_�́A�e���X�̕��ł���B1~2 mm�́g�ُ�Ƃ��v����L���̕��q�I�ɕ����ȃe���X�h���ϑ�����A�e���X��ɂ́A�g�A�C�����h�̗l�Ȍ��ׁh��������Ȃ��B
�}�P�O�́A����ώ@�̈�i5 mm�l���j�Ŕ�r�����������ƒP������AFM���������B���̈Ⴂ�͋������̂ł������B
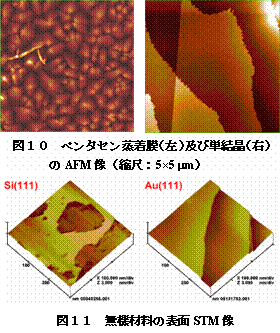 �O�q�����悤��Si(111)�AGaAs�AInP���̔����̕\�ʂ̌��q���x���ł̉t���G�b�`���O�ߒ������������B�X�ɁAAu�APt�ARh�AIr�APd�ANi�ACo���̋M�����P�����\�ʂ̌��q�\�����𖾂��Ă����B���Ӑ[���������ꂽ��L�����̂���ыM�����ł��A�e���X�̍L����10~100 nm���x�ł���B�}�P�P�ɂ́A�t���œ���ꂽSi(111)�����Au(111)�\�ʂ�STM�����Ƃ��Ď������B�ϑ��̈�͗��҂Ƃ�0.3 mm�l���ł���B�}�P�O�Ɛ}�P�P�̔�r������A���q���y���^�Z���P�����́A���ɐ��~�N�����ɓn��e���X����L���Ă���B����܂ł̌o�����炷��ƁA���q���P�����Ŋϑ����ꂽ�e���X���́A�ُ�Ƃ��v�����L���A�t���ō��ꂽ���q�������̊��S���������������Ă�����̂ƍl������B�X�ɏd�v�Ȏ��́A�����ł͏ڍׂɏq�ׂȂ����A���̏d�v�ȗL�@�����̂ł���A���u�����A�e�g���Z���A�R���l�����̒P���������S���̍��������ł������B
�O�q�����悤��Si(111)�AGaAs�AInP���̔����̕\�ʂ̌��q���x���ł̉t���G�b�`���O�ߒ������������B�X�ɁAAu�APt�ARh�AIr�APd�ANi�ACo���̋M�����P�����\�ʂ̌��q�\�����𖾂��Ă����B���Ӑ[���������ꂽ��L�����̂���ыM�����ł��A�e���X�̍L����10~100 nm���x�ł���B�}�P�P�ɂ́A�t���œ���ꂽSi(111)�����Au(111)�\�ʂ�STM�����Ƃ��Ď������B�ϑ��̈�͗��҂Ƃ�0.3 mm�l���ł���B�}�P�O�Ɛ}�P�P�̔�r������A���q���y���^�Z���P�����́A���ɐ��~�N�����ɓn��e���X����L���Ă���B����܂ł̌o�����炷��ƁA���q���P�����Ŋϑ����ꂽ�e���X���́A�ُ�Ƃ��v�����L���A�t���ō��ꂽ���q�������̊��S���������������Ă�����̂ƍl������B�X�ɏd�v�Ȏ��́A�����ł͏ڍׂɏq�ׂȂ����A���̏d�v�ȗL�@�����̂ł���A���u�����A�e�g���Z���A�R���l�����̒P���������S���̍��������ł������B
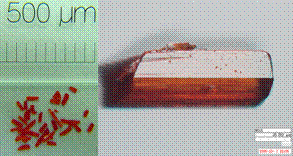 ���u�����F�@�d�q�f�o�C�X�ւ̉��p��ڎw���āA�n�t����̒P�����̐����Ƃ�����{�I�e�[�}�Ɋւ��n���I�Ȍ������s���Ă����B�L�@FET�̌����Ńy���^�Z���ƕ���ő����̌������Ȃ���Ă��郋�u�����̗n�t����̒P�����̐����ɂ��y���^�Z���Ɣ��ɐ������Ă���B�}�P�Q�́A���u�����̃N�����t�H�����n�t�Ƀw�L�T���̏��C���g�U���鎖�ɂ���ē���ꂽ�A���u���������̎ʐ^�ł���B�����ł������B
���u�����F�@�d�q�f�o�C�X�ւ̉��p��ڎw���āA�n�t����̒P�����̐����Ƃ�����{�I�e�[�}�Ɋւ��n���I�Ȍ������s���Ă����B�L�@FET�̌����Ńy���^�Z���ƕ���ő����̌������Ȃ���Ă��郋�u�����̗n�t����̒P�����̐����ɂ��y���^�Z���Ɣ��ɐ������Ă���B�}�P�Q�́A���u�����̃N�����t�H�����n�t�Ƀw�L�T���̏��C���g�U���鎖�ɂ���ē���ꂽ�A���u���������̎ʐ^�ł���B�����ł������B
�}�P�Q���u�����P�����@
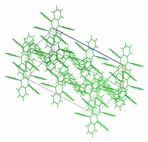

![]() ����ɁA�P�ꌋ���̂w����͂ɂ��A�\��������s�����B�}�P�R�i���j�́A�Q������܃p�^�[���̂P��ł��邪�A�ǎ��ȒP�����������鎖�����������B�ڍׂȉ�͂���A�E�}�Ɏ����\����L���Ă���A����܂ł̊����X-����͌��ʂƈ�v�����B�C���g�U�@�ɂ����@�ł����u�����P�������������A����X-���\����͂��s�������AX���I�ɂ͗��҂Ƃ��ǍD�ȒP�����ł������B
����ɁA�P�ꌋ���̂w����͂ɂ��A�\��������s�����B�}�P�R�i���j�́A�Q������܃p�^�[���̂P��ł��邪�A�ǎ��ȒP�����������鎖�����������B�ڍׂȉ�͂���A�E�}�Ɏ����\����L���Ă���A����܂ł̊����X-����͌��ʂƈ�v�����B�C���g�U�@�ɂ����@�ł����u�����P�������������A����X-���\����͂��s�������AX���I�ɂ͗��҂Ƃ��ǍD�ȒP�����ł������B
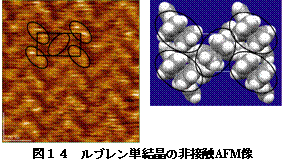 ��ڐG���q�Ԍ������̕��q����\�̒B��
��ڐG���q�Ԍ������̕��q����\�̒B��
�@���x�ɍ\���K�����ꂽ���q�������̓d�q�f�o�C�X�ւ̉��p��i�߂邽�߂ɂ́A���w�̕��q�w�A����ɂ́A����ȏ�̐ϑw���̍\���q���x���Ŕc������K�v���L��B��\�҂����N�|���Ă����t��STM�́A���w�̋z���w�̍\���Ɋւ��ċɂ߂ėL�p�ȏ���^���邪�A�g���l���d���𐧌���q�ɂ���STM�ł́A�≏�̂ɋ߂��ݐϖ��ɂ͓K�p�ł��Ȃ��B
�}�Q�O�@���u�����P�����̌��w�������ʐ^
�@�������A�ŋ߂��̐i������������ڐG���q�Ԍ������iNC-AFM�j�́A���̌�������A�≏�̂ł�����ΏۂɂȂ�A�������A�^�̌��q�E���q����\�œ����鎖���m���������B���������ɂ����āA�{�����J���ɂ͕K�v�s���Ȏ�@�Ƃ̔F������A��R�N�ԁA���u�i���{�d�qUHV-AFM�j�̓����A������@�̎��n�A�P�����̍������@�̒T���A����i�߂��B���̌��ʁA�ŋ߁A�L�@FET�ł��d�v�ȃ��u�����P�����̕\�ʕ��q���̊ώ@�ɐ��������B���̐��ʂ́A�_�˂ōs��ꂽ��ڐGAFM�̍��ۉ�c�Ŕ��\�����iInternational Conference on NC-AFM, 2006,
July, 16-20, Kobe�j�B
�@�}�P�S�ɂ́A�t���@����쐬�������u�����P�����\�ʂ̒����^�ł̐��E�ŏ��߂Ă̕��q���ł���BNC-AFM���̒��őȉ~�Ŏ��������q���P�̃��u�������q�ł���A�ڍׂȉ�͂̌��ʁA���u�����̕\�ʍ\���́A�}�Q�P�ŏq�ׂ��o���N�̌����\����������ł���B�č\���\���͎���Ă��Ȃ��B
�@�}�P�S�̗l��NC-AFM������AX-����ܖ@��p�����Ƃ��A�����̐��m�ȕ��ʌ���̉\�ł���A�{�����J����i�߂��ŁA�ɂ߂ďd�v�ȑ����i�ł���B
�@����A���̎�@���t�̒��ɓK�p���鎖���\�ƂȂ�A���������̂��̏�ώ@���\�ƂȂ�A�t�����������@�̊m���ɂƂ��ďd�v�Ǝv����B
�Q�l����
�P�jK. Suto, S. Yoshimoto, and K. Itaya,
"Two-Dimensional Self-Organization of Phthalocyanine and Porphyrin:
Dependence on the Crystallographic Orientation of Au", J. Am. Chem. Soc., 125(49)�A14976–14977(2003).
�Q�jS. Yoshimoto, E. Tsutsumi, Y. Honda, Y. Murata,
M. Murata, K. Komatsu, O. Ito, and K. Itaya, �gControlled Molecular Orientation
in an Adlayer on Au(111) of a Supramolecular Assembly Consisting of an
Open-Cage C60 Derivative and Zn(II) Octaethylporphyrin�h, Angew.
Chem. Int. Ed., 43, 3044–3047 (2004).
�A�ꎟ���L�@����
�L�@�����̋y�ѓ��̂̌����ɂ����āATTF�n�U���̂́A�≏�̂��璴�`���̂ɓn��L�͂ȕ�����^���邱�Ƃ���A�������錤���Ώۂł���BTTF�n�U���̂�p����FET�̍쐻�ɂ��ẮA����̕��Ȃ���Ă���B������\�҂͈ꎲ�����Ɍ�������������DT-TTF�i�}�P�P�j�̏d�v���Ɋӂ݁A�t�������DT-TTF�P�����쐻�Ƃ���FET�ɂ��Č�����i�߂Ă���BDT-TTF�͍������ȒP�ł͂Ȃ��A���ݎs�̂���Ă��Ȃ����߁A�V�KTTF�n�U���̂̊J���ƍ��̂̕�����������Ƃ��Ă��鋤�������ҁA���Ɍ�����w�̎R�c���ꏕ�����Ƌ���������i�߂Ă���B���ɁA�}�P�U�Ɏ����悤�ɗn�t����̒P�����쐻�Ƃ��̐����ߒ��̘A���ϑ����s���A���݁AFET�f�q�̍쐻��i�߂Ă���B�t�����瓾��ꂽDT-TTF�P��������ɏq�ׂ��y���^�Z���Ɠ��l�ɕ��q���x���ŕ��R�ȕ\�ʍ\���������Ƃ�AFM�ɂ��\�ʊϑ��ɂ�莦����A�n�t�v���Z�X�ɂ��ǎ��ȒP�����邱�Ƃ��o���邱�Ƃ��������B�{�����ł́ADT-TTF�⑼��TTF�n�U���́A����ɐV�KTTF�U���̂ɂ��āA�C���y�щt���v���Z�X��p�����P�����쐻�A����AFM�ϑ��A�����FET�����̑�����s���ATTF�U���̂�p�����L�@�G���N�g���j�N�X�f�q�̌�����i�߂Ă����B
3.2�I���S���S�`�I�t�F��
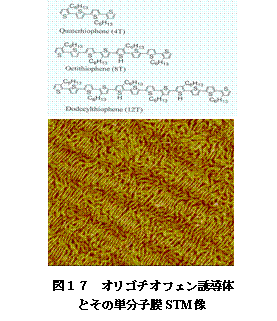
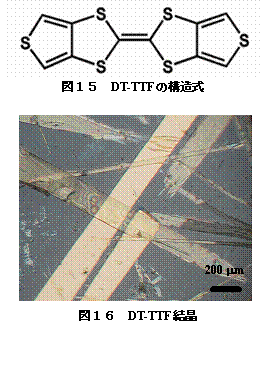 �`���������q�̓`���@�\�Ƃ��֘A���A�h�i�[���̍����|���`�I�t�F���A���̕��q�����K�肳�ꂽ�I���S�`�I�t�F���̐��E�ړ��x�͋����̂��镨���ł���B����܂ł́A�\�����䂳��Ă��Ȃ��|���`�I�t�F���A���邢�́A�I���S�`�I�t�F��������FET����������Ă��邪�A�{�����J���ł́A�I���S�`�I�t�F�������x�ɔz�������������쐻���A���E�ړ��x�ƕ��q���̕����Ƃ̊W�����߂钧��I�ۑ�Ɏ��g�ށB����܂ōs�����̂́A�P�Q�̃��j�b�g���A�������AT12��Au(111)�ʏ�ł̋z���\���ł���B
�`���������q�̓`���@�\�Ƃ��֘A���A�h�i�[���̍����|���`�I�t�F���A���̕��q�����K�肳�ꂽ�I���S�`�I�t�F���̐��E�ړ��x�͋����̂��镨���ł���B����܂ł́A�\�����䂳��Ă��Ȃ��|���`�I�t�F���A���邢�́A�I���S�`�I�t�F��������FET����������Ă��邪�A�{�����J���ł́A�I���S�`�I�t�F�������x�ɔz�������������쐻���A���E�ړ��x�ƕ��q���̕����Ƃ̊W�����߂钧��I�ۑ�Ɏ��g�ށB����܂ōs�����̂́A�P�Q�̃��j�b�g���A�������AT12��Au(111)�ʏ�ł̋z���\���ł���B
�}�P�V�́A���������ҁA�L����w�A��@�O�v�����̍��������AT12��Au(111)�ʏ�ɋz�������A�P���q����STM���ł���B��̗���͗L����̂́A�K���I�ɔz�Ă��鎖���A���������B���̕\�ʂŌ����������s���ƁA��P�w�ڂ̋z���\���ƃo���N�̌����\�����ւ��A���q���x���ʼn𖾂��邱�Ƃ����҂����B�|���`�I�t�F���ł͑�P�w�̋z���\��������Ă��邪�A�I���S�}�[�ł͔�r�I�����K����������B�d���������q�̋K���\���Ɠd�q�I�����̑��ւ����炩�ɐ���\���������B
4.�܂Ƃ�
�u�ʼnt�E�ʁv�Ő������镪�q�������̓������ő�����p���A�����@�ł͓����Ȃ��A���i�ʂ̕��q���P������d�q�f�o�C�X�ɉ��p���悤�Ƃ�����̂ł���B�n�t���g�p����E�G�b�g�v���Z�X�́A���̗e�Ղ�����A���͂���H�ƓI�����v���Z�X�ł��邪�A�t�̒��ł̌����Ɨn�t�̊E�ʂ́A�ʏ�̕��@�ł́A���q���x���̒m���鎖�͗e�Ղł͂Ȃ��A�w�ǂ̊����̃E�G�b�g�v���Z�X�́A�o���ƃm�E�n�E�ŋZ�p���\�z����Ă���B�����������_�q���x�����猟�����āA��r�I���\�v�����������d�q�f�o�C�X�ւ̓K�p�����݂���̂ł���B
�u�ʼnt�E�ʁv�����p�����H�ƓI�����v���Z�X�́A�S�|�A�Ɠd�A���w�A�\�ʏ����A���̎�v����ő����̗p����Ă���A�{�����J���̐��ʂ́A�d�q�f�o�C�X�݂̂Ȃ炸�A�����̊����̐����v���Z�X�ɑ���ȉe����^������̂ƍl������B�X�ɂ́A���ȑg�D���A�{�g���A�b�v���Ŋ��҂���Ă��镪�q�f�o�C�X�ւ̏d�v�ȕ��@�_�Ƃ��Ĕ��W������̂Ǝv����B
�i�m�e�N�m���W�[�́A�S���E�Ō����J�����i��ł��閲�Ɗ��҂̑�������ł���䂪���̏����̉Ȋw�Z�p���x����ۑ�̂P�ł���B�{�e���A�i�m�e�N�m���W�[�̊�ՋZ�p�̒T���Ɉꏕ�ɂȂ�K���ł���B